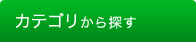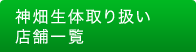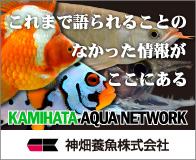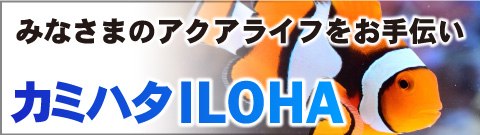珍奇!ヒゲミズヘビ

この不思議な生き物がヒゲミズヘビです。
おそらく、世界で最も奇妙なヘビの一つでしょう。
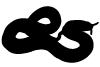 ヒゲミズヘビとは?
ヒゲミズヘビとは?
ヒゲミズヘビErpeton tentaculatumは、カンボジア、タイ、ベトナムなどに生息する、非常に奇妙なヘビで、
ミズヘビ科、ヒゲミズヘビ属に分類されており、1種のみでヒゲミズヘビ属を構成しています。
全長60cm〜100cm。体重140g〜200gほどで、雌雄でサイズに差は見られないようです。体色はブラウンに暗色のストライプ柄ものと、
黒褐色にブロッチ柄が並ぶ、2タイプが存在しますが、それらが単なる個体差なのか、生息地による差なのか、はっきりしたことは、わかっていません。
鱗には強いキール(隆起)があり、触ると紙ヤスリのようです。これは水中で自身の体を枝などに巻き付けて固定する際や、餌となる魚などを捕らえた時に役立つと考えられています。
また、腹鱗(いわゆる蛇腹)は退化しており、陸上ではゆっくりとしか動くことができません。なお、人体には影響が無いと思われますが、奥歯に毒牙を備えた後牙類で、
捕らえた魚の動きを短時間で止めることができます。
性質はおとなしく、咬みついたりはしません。危険を感じると体を棒のように硬直させます。おそらく擬死(死に真似)、もしくは、枝に擬態しているのでしょう。
繁殖形態は卵胎生で、1度に3匹〜15匹の仔ヘビを水中で出産します。希ですが、日本国内でも出産された記録があります。
野生下では、水草などが多く生えた流れの遅い河川や池に生息し、弱酸性の水質を好みます。水から上がることはほとんどありませんが、
水が干上がるような乾期は、泥の中に潜って過ごします。
野生下での食性はよくわかっていません。主に魚類を補食していると考えられていますが、オタマジャクシなどの両生類から、エビなどの甲殻類を補食したという記録もあります。
ヒゲミズヘビを含むミズヘビの仲間は、東南アジアでは食用として古くから利用されており、近年では、養殖用のワニの餌としても利用されています。




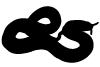 ヒゲミズヘビの“髭”の役割は?
ヒゲミズヘビの“髭”の役割は?
本種の最大の特徴と言える、2本の髭状の突起ですが、かつては『枝に擬態するためにある』とか、『水中で動かして、餌動物をおびき寄せるためにある』など様々な説がありましたが、
真相は永らく不明のままでした。しかし近年、アメリカの研究グループが“髭”の役割を解明しました。
ヒゲミズヘビの髭状の突起には、味覚や触覚などに関係する神経細胞が埋め込まれていることがわかりました。ヒゲミズヘビの髭は、僅かな水の動きを感知し、
獲物をつかまえるための器官だったのです。このおかげで、ヒゲミズヘビは水が濁っていても、真っ暗な中でも、正確に獲物を捕獲する事ができるのです。
なお、餌の捕獲方法ですが、完全な待ち伏せ型で、水中で体をS字型ないし、J字型に曲げ、獲物が近づくまで、じっと待ち伏せます。そして獲物が射程距離に入った瞬間、
電光石火の素早さで咬みつき、そのまま飲み込んでいきます。もしも獲物が大きい場合は、体の前部で締め付ける事もあります。
たった100cm足らずの小さなヘビですが、その体には様々な工夫が凝らされており、まさに大自然の凝縮のような動物です。

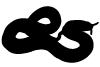 飼育は熱帯魚感覚で
飼育は熱帯魚感覚で
ヒゲミズヘビはほぼ完全な水中生活を送るので、熱帯魚感覚で飼育することができます。ただし、念のため蓋だけはきっちり閉めたほうがよいでしょう。
飼育温度は26℃前後、水量は多め、水質は弱酸性、水流は穏やかに設定します。なお、ヒゲミズヘビは水中でつかまる場所が必要なので、必ず水草や流木などでレイアウトします。
餌はメダカや金魚でかまいません。餌の量はサイズや状態によって異なりますが、成体なら1週間に金魚を20〜30匹ぐらい食べることがあります。大食漢に聞こえるかもしれませんが、
マウスを丸呑みする一般的なヘビに比べると、魚はずいぶん軽いお食事です。寿命に関しては、まだよくわかっていませんが、10年〜20年ほどと思われます。


丸い頭に円筒形の体を持ち、これがベーシックなミズヘビの形状といえます。

ほとんどは擬態のためと考えられています。もしかしたら、ヒゲミズヘビのような
特殊能力が隠されている種類が、今後も見つかるかもしれません。
ヒゲミズヘビ特集、いかがでしたでしょうか?ヒゲミズヘビは、数あるヘビの中でも、まさに唯一無二の存在であり、洗練された、実に美しいハンターです。 そして、その不思議な生態を、水槽内で実際に観察できるなんて、なんとも贅沢な経験ではないでしょうか。見ているだけで時間を忘れさせてくれる、そんな魅力を持った動物です。