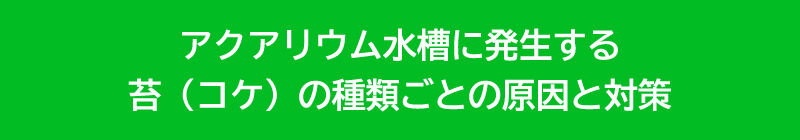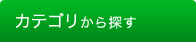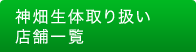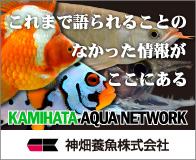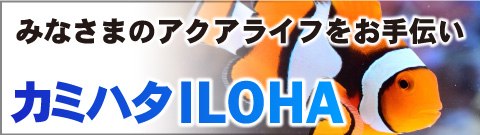アクアリウム水槽に発生する苔(コケ)の除去や掃除をしてくれる生物たち
|
アクアリウム水槽に発生する苔(コケ)の除去や掃除をしてくれる生物たち
目次
1.アクアリウム水槽向きの苔(コケ)取り生物
●アクアリウム水槽で発生するコケとそれを食べてくれるいきものアクアリウム水槽で発生するコケは鑑賞上美しくなく、また水草の葉の表面に発生すれば、水草の成長を阻害することにもつながります。そのため、コケの駆除や対策はアクアリウムにおいて重要な課題です。コケを抑えるためには様々な手段がありますが、水槽で発生するコケの予防や駆除に役立つ強力な助っ人となるのが「コケを食べるいきもの」たちです。
アクアリウムでは、このコケを食べる水槽内の生き物を「コケ取り生物」と呼んでいます。それぞれのコケ取り生物には好んで食べるコケ、あまり食べないコケがあり、全てのコケをまんべんなく食べてくれる生物はいません。そのため、自分の水槽にはどのコケ取り生物が最適なのか見極める必要があります。
ここではコケ取り生物にスポットを当てて、それぞれの生物が好んで食べるコケの種類や導入匹数の目安、導入時の注意点などをご紹介していきます。またコケの種類、コケごとの予防策、対策などは別ページで詳しくご紹介しています。まずはそちらもご覧いただき、各コケの特徴を掴んでいただくと良いかと思います。
1-1.ヤマトヌマエビ
| よく食べるコケ |
水草の葉・茎、石、流木表面の茶ゴケ、柔らかめ・硬めの糸状ゴケ |
| あまり食べないコケ |
ガラス面の茶ゴケと緑ゴケ、硬いマット状の緑ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・5〜10匹 |
| コケが少ない場合・・・2〜3匹 |
| 飼育可能水温 |
15〜27℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜8.0 |
| 最大サイズ |
5cm |
| 平均寿命 |
2〜3年 |
|
|
|
|
【特徴】
コケ取り生物として定番の日本産のヌマエビの仲間です。糸状の緑藻、珪藻を特に好んで食べ、特に他に食べてくれる生物が少ない硬めの糸状の緑藻(アオミドロの仲間)も好むため非常に重宝します。手では取れない水草の葉の表面や茎などの細かい部分を常に掃除してくれるので水草自体もキレイに保ってくれます。細かい部分のコケ取りには向いていますが、ガラス面などの広い面積のコケ取りには不向きです。魚の残した沈んだエサも食べてくれます。水槽内では抱卵まではいきますが、稚エビは汽水性のため殖えることはほとんどありません。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・立ち上げ直後のアンモニア・亜硝酸塩が検出される水槽への導入は控える
- ・水草水槽では無給餌でもOK ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・大きな魚には食べられてしまう ・コケのみならず水草の葉も食べてしまったり、抜いてしまうことがある(特に、葉が柔らかい種類、トリミング直後、前景草の根張り前、水中葉化の途中などは特に注意が必要で、匹数を少なくする、しばらくしてから導入するなどの工夫をする)
|
1-2.ミナミヌマエビ(&チェリーシュリンプ系)
| よく食べるコケ |
水草の葉・茎、石、流木表面の茶ゴケ、柔らかめの糸状ゴケ |
| あまり食べないコケ |
ガラス面の茶ゴケと緑ゴケ、硬いマット状の緑ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・50〜60匹 |
| コケが少ない場合・・・10〜30匹 |
| 飼育可能水温 |
5〜28℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜7.5 |
| 最大サイズ |
2〜3cm |
| 平均寿命 |
1〜2年 |
|
|
|
|
|
【特徴】
ヤマトヌマエビを小さくしたような外見の小型のエビです。1匹あたりのコケ取り能力はヤマトヌマエビよりも劣りますが、数を多く入れれば柔らかい珪藻が発生する水槽などで効果を発揮します。ヤマトヌマエビと違い、水槽内で繁殖できるため、ゆくゆくは殖えることでさらなる効果が期待できます。また近縁種であるレッドチェリーシュリンプやイエローチェリーシュリンプなどは、観賞のために飼育される場合が多いですが、ミナミヌマエビと同様に水槽内で殖えてコケも食べるので、コケ取り生物としても有能です。魚の残した沈んだエサも食べてくれます。飼育可能な水温の幅が広く、加温なしの水槽や屋外飼育にも向いています。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・立ち上げ直後のアンモニア・亜硝酸塩が検出される水槽への導入は控える
- ・水草水槽では無給餌でもOK ・水草への食害はほとんどない
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・成長しても小さい種類の為、小型魚のみとの混泳がオススメ
|
1-3.オトシンクルス・オトシンネグロス
| よく食べるコケ |
水草の葉・茎、石、流木表面のマット状の茶ゴケ、緑ゴケ |
| あまり食べないコケ |
硬い糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・5〜10匹 |
| コケが少ない場合・・・2〜3匹 |
| 飼育可能水温 |
22〜29℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜7.5 |
| 最大サイズ |
5cm |
| 平均寿命 |
3〜4年 |
|
|
|
|
【特徴】
小型のナマズの仲間で、水槽底面やガラス面、葉の上などに張り付いてじっとしていることが多く、泳ぎ回ることはありません。水草水槽向きのコケ取り魚の中で最も有名です。水槽ガラス面や幅の広い水草の葉の表面に生えるマット状のコケを良く食べ、硬めの緑藻も食べてくれます。ツルツルした面のコケ取りが得意で、逆に細かい入り組んだ部分のコケ取りには不向きです。1匹あたりのコケ取り能力はそれほど高くないので多めに導入すると効果を実感しやすいです。クルスよりネグロスの方が丈夫で、コケ取り能力も高いと言われています。また水槽内で繁殖しやすいのもネグロスです。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・水草水槽では無給餌でもOKな場合もあるが、痩せ具合を見ながらエサが足りていないようならプレコタブレットなどを与える
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・稚魚や稚エビは食べてしまうことがある
- ・大きくならないため、小型水槽にもオススメ
|
1-4.サイアミーズフライングフォックス・シルバーフライングフォックス
| よく食べるコケ |
水草の葉・茎、石、流木表面の柔らかいマット状の茶ゴケ、短い糸状ゴケ、生えたての黒ヒゲ状のコケ・カワモズク |
| あまり食べないコケ |
硬いマット状・糸状ゴケ、成長しきった黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・5〜10匹(4cmサイズ) |
| コケが少ない場合・・・2〜3匹(4cmサイズ) |
| 飼育可能水温 |
22〜29℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜8.0 |
| 最大サイズ |
10〜15cm |
| 平均寿命 |
4〜5年 |
|
|
|
|
【特徴】
おちょぼ口が特徴的な見た目で中層をホバリングしたり、水槽内を泳ぎ回ります。もともとコケ取り能力の高い魚ですが、水草水槽の立ち上げ時には特に効果的です。水草や石、流木に生える柔らかい茶ゴケ、緑ゴケを好んで食べ、表面をキレイに保ってくれますが、立ち上げ直後の不安定な環境にも比較的強く、水質に敏感なエビ類が入れられない場合にも活躍してくれます。サイアミーズよりもシルバーの方がコケ取り能力が高いと言われていますが、シルバーの方がやや大きくなる傾向もあるようです。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・水草水槽では無給餌でもOKな場合もあるが、痩せ具合を見ながらエサが足りていないようなら顆粒・フレーク状のものを与える
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・大きくなり、なわばりを持つと他の魚を追い払うことがある
- ・稚魚や稚エビは食べてしまうことがある
- ・泳ぐ力が強いため飛び出し注意
|
1-5.アルジーイーター・ゴールデンアルジーイーター
| よく食べるコケ |
水槽ガラス面、石、流木表面のマット状の茶ゴケ、緑ゴケ |
| あまり食べないコケ |
硬い糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・5〜10匹(4cmサイズ) |
| コケが少ない場合・・・2〜3匹(4cmサイズ) |
| 飼育可能水温 |
22〜29℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜8.0 |
| 最大サイズ |
25cm |
| 平均寿命 |
10〜15年 |
|
|
|
|
【特徴】
サイアミーズフライングフォックスに似ていますが、こちらは水槽ガラス面、石、流木などに張り付いてじっとしていることが多く、あまり泳ぎ回りません。水槽ガラス面、石や流木表面のコケ取りが得意で、硬いコケもしっかり食べてくれる強力な生物です。成魚は気が強い面がありますので混泳には注意が必要です。立ち上げ直後の不安定な環境にも比較的強く、水質に敏感なエビ類が入れられない場合にも活躍してくれます。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・水草水槽では無給餌でもOKな場合もあるが、痩せ具合を見ながらエサが足りていないようなら顆粒・フレーク状のものを与える
- ・エサに慣れて10cm以上になるとあまりコケを食べなくなる
- ・成魚は大きくなり、気性も荒くなるので大型水槽向き
- ・小型の魚やエビは食べてしまうことがある
|
1-6.ブラックモーリーなどの小型モーリー
| よく食べるコケ |
藍藻、水面に浮かぶ油膜に似たコケ(緑藻の仲間)、水草の葉・茎、石、流木表面の茶ゴケ、柔らかめの糸状ゴケ |
| あまり食べないコケ |
硬いマット状・糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・4〜5匹 |
| コケが少ない場合・・・1〜2匹 |
| 飼育可能水温 |
22〜27℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜8.0 |
| 最大サイズ |
5〜7cm |
| 平均寿命 |
1〜2年 |
|
|
【特徴】
グッピー、プラティに並んで、アクアリウムでは有名な魚です。藍藻や水面に浮かぶ油膜状の緑藻を好んで食べ、これ以外にも柔らかい茶ゴケ、緑ゴケも食べてくれる生物です。モーリーの仲間には数種類いますが、コケをよく食べてくれるのはブラックモーリー、オレンジ(ライヤー)モーリー、シルバー(ライヤー)モーリーなどのスフェノプス系で、ベリフェラ系(セルフィン、バルーンモーリーなど)はコケ取り能力は弱い傾向があります。雌雄で飼育すれば水槽内で殖えてくれます。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・水草水槽では無給餌でもOKな場合もあるが、痩せ具合を見ながらエサが足りていないようなら顆粒・フレーク状のものを与える
- ・オスが繁殖しようとメスを追いかけることがあるため、ペアで入れる、数をたくさん入れる、雌雄どちらかだけ(メスのみがケンカもなくオススメ)入れる
- ・小型の魚やエビは食べてしまうことがある
|
|
【藍藻を除去する時のポイント】
藍藻は増殖が非常に早く、生物だけでは完全除去が難しくなかなか減少しない厄介なコケです。発生してしまった場合は、アンチグリーンを併用することでよりスムーズに駆除することが可能です。
|

|
|
アンチグリーンを用いたコケ対策や水草育成事例を詳しく紹介しています。
|
|
1-7.セルフィンプレコ
| よく食べるコケ |
水槽ガラス面、石表面の茶ゴケ、緑ゴケ |
| あまり食べないコケ |
糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
5〜6cmサイズで1匹 |
| 飼育可能水温 |
23〜29℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜8.0 |
| 最大サイズ |
30cm以上 |
| 平均寿命 |
10〜15年 |
|
|
|
|
【特徴】
全身の黒いスポットが特徴のナマズの仲間で、水槽ガラス面、石、流木などに張り付いてじっとしていることが多く、泳ぎ回ることはありません。コケ取りのプレコといえばこの種類というくらい有名な魚で、たいていのアクアリウムショップで販売されています。水槽ガラス面、石の表面のコケ取り能力はかなり強力でコケ取りの魚の中では最強と言っても過言ではありません。かなり硬いコケまでバリバリはがして食べてくれます。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・水草水槽では無給餌でもOKな場合もあるが、痩せ具合を見ながらエサが足りていないようならプレコタブレットを与える
- ・小型のエビは食べてしまうことがある
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能だが、大型の魚の体表に張り付き、傷を付けてしまうことがある
|
1-8.スポッテッドブッシ―マウスプレコ・アルビノブッシ―マウスプレコ
| よく食べるコケ |
水槽ガラス面、石表面の茶ゴケ、緑ゴケ |
| あまり食べないコケ |
糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
5〜6cmサイズで2匹 |
| 飼育可能水温 |
23〜29℃ |
| 飼育可能pH |
5.5〜8.0 |
| 最大サイズ |
15〜20cm |
| 平均寿命 |
8〜10年 |
|
|
|
|
|
|
【特徴】
全身の白いスポットが特徴のナマズの仲間で、水槽ガラス面、石、流木などに張り付いてじっとしていることが多く、泳ぎ回ることはありません。セルフィンプレコと並び、コケ取りのプレコとして有名です。水槽ガラス面、石の表面のコケを好んで食べ、セルフィンプレコほどは大きくなりません。他にもロングフィンタイプなどの改良品種もいますが同様にコケを食べてくれます。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・水草水槽では無給餌でもOKな場合もあるが、痩せ具合を見ながらエサが足りていないようならプレコタブレットを与える
- ・稚エビは食べてしまうことがある
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
|
1-9.イシマキガイ・シマカノコガイ
| よく食べるコケ |
水槽ガラス面、石、流木表面の茶ゴケ、緑ゴケ |
| あまり食べないコケ |
糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・5〜10匹 |
| コケが少ない場合・・・3〜4匹 |
| 飼育可能水温 |
10〜27℃ |
| 飼育可能pH |
6.0〜8.0 |
| 最大サイズ |
2〜3cm |
| 平均寿命 |
1〜2年 |
|
|
|
|
|
|
【特徴】
コケ取り貝の定番種です。水槽ガラス面、石、流木の表面のコケを好んで食べてくれます。ある程度の低温にも耐えられますのでヒーター無しの金魚、メダカ水槽にも導入できます。魚が残した沈んだエサも食べてくれます。水槽内でよく産卵しますが汽水性のため、殖えることはほとんどありません。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・pHが低すぎる(6以下)と活動停止してしまう
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・水槽から脱走することがあるのでフタやフチ有り水槽がオススメ
- ・ひっくり返って起き上がれない事があるので気付いたら起こしてあげる
|
1-10.フネアマガイ
| よく食べるコケ |
水槽ガラス面、石、流木表面の茶ゴケ、緑ゴケ |
| あまり食べないコケ |
糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク、藍藻 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・3〜4匹 |
| コケが少ない場合・・・1〜2匹 |
| 飼育可能水温 |
15〜27℃ |
| 飼育可能pH |
6.0〜8.0 |
| 最大サイズ |
4cm |
| 平均寿命 |
1〜2年 |
|
|
|
|
【特徴】
水槽ガラス面、石、流木の表面のコケ取り能力はかなり強力で最強と言っても過言ではありません。ある程度の低温にも耐えられます。水槽内でよく産卵しますが汽水性のため、殖えることはほとんどありません。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・pHが低すぎる(6以下)と活動停止してしまう
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・水槽から脱走することがあるのでフタやフチ有り水槽がオススメ
- ・ソイルの中まで入り込んでしまうことがある
- ・ひっくり返って起き上がれない事があるので気付いたら起こしてあげる
|
1-11.ゴールデンアップルスネール・レッドラムズホーン
| よく食べるコケ |
藍藻、水槽ガラス面、石、流木表面の茶ゴケ、緑ゴケ |
| あまり食べないコケ |
糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・5〜10匹 |
| コケが少ない場合・・・3〜4匹 |
| 飼育可能水温 |
20〜28℃ |
| 飼育可能pH |
6.0〜8.0 |
| 最大サイズ |
4cm |
| 平均寿命 |
1〜2年 |
|
|
|
|
|
|
【特徴】
見た目の美しさから観賞用として飼育される方も多いですが、コケ取り能力もあり、特に藍藻対策に活躍します。活発に動き、魚の残したエサも良く食べてくれ、藍藻予防としても効果的です。条件が合えば水槽内でたくさん殖えます。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・pHが低すぎる(6以下)と活動停止してしまう
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・水槽から脱走することがあるのでフタやフチ有り水槽がオススメ
- ・水草も食べてしまうことがある
|
|
【藍藻を除去する時のポイント】
藍藻は増殖が非常に早く、生物だけでは完全除去が難しくなかなか減少しない厄介なコケです。発生してしまった場合は、アンチグリーンを併用することでよりスムーズに駆除することが可能です。
|

|
|
アンチグリーンを用いたコケ対策や水草育成事例を詳しく紹介しています。
|
|
1-12.タニシ
| よく食べるコケ |
水槽ガラス面、石、流木表面の茶ゴケ・緑ゴケ、アオコ |
| あまり食べないコケ |
糸状ゴケ、黒ヒゲ状のコケ・カワモズク |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
コケが多い場合・・・10〜20匹 |
| コケが少ない場合・・・5〜10匹 |
| 飼育可能水温 |
10〜30℃ |
| 飼育可能pH |
5.0〜8.0 |
| 最大サイズ |
6〜7cm |
| 平均寿命 |
2〜3年 |
|
|
|
|
【特徴】
他のコケ取りの貝類に比べて能力はそれほど高くありませんが、国産かつ純淡水性のおかげで、飼育可能な水温・水質の幅が広いのが魅力と言えます。水槽内で殖えますが、石などに卵を産み付けるタイプではないため、鑑賞面も問題ありません。また通常のコケだけでなく、水中の植物プランクトンなどの濾過摂食もおこなっています。これらの理由からビオトープなどの屋外環境にも適しています。また魚の残したエサだけでなく、そのフンなどのデトリタスも食べてくれるため、水槽内をよりキレイに保てます。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
- ・他の貝類よりもやや多めに入れる
- ・大食漢でフンをたくさんするのでしっかり掃除をする
|
1-13.淡水シジミ・二枚貝の仲間
| 淡水シジミ |
| よく食べるコケ |
アオコ |
| あまり食べないコケ |
水中に浮遊しないコケ全般 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
20〜30匹 |
| 飼育可能水温 |
10〜25℃ |
| 飼育可能pH |
6.0〜8.0 |
| 最大サイズ |
3cm |
| 平均寿命 |
1〜2年 |
| ドブガイ・イシガイなどの二枚貝の仲間 |
| よく食べるコケ |
アオコ |
| あまり食べないコケ |
水中に浮遊しないコケ全般 |
| 60cm水槽 導入数(目安) |
2〜3匹 |
| 飼育可能水温 |
5〜22℃ |
| 飼育可能pH |
6.0〜8.0 |
| 最大サイズ |
10〜15cm |
| 平均寿命 |
10年以上 |
|
|
|
|
【特徴】
アオコが発生した時に活躍してくれる濾過摂食をおこなう二枚貝です。長期飼育のためにはアオコがなくなった後のエサを確保する必要があり、継続的にグリーンウォーター化するような環境が好ましいです。ドブ貝、イシ貝などはタナゴの産卵床としても用いられます。
|
【導入時のコツ・注意点】
- ・導入時にpHが大きく異なる場合は水合わせ時間を長めに(数時間程度)取る
-
- ・pHが低すぎる(6以下)と活動停止してしまう
-
- ・高水温に弱い
-
- ・他の生物に危害を加えることはほとんどなく、様々な生物と混泳可能
-
- ・アオコが解消された後のエサの供給方法も考えておく
-
|
|

【苔(コケ)の種類ごとの原因と対策】
アクアリウムの悩みのタネであるコケについて、コケとはそもそもどんなもので、何が原因で発生するのか。また発生させないための予防策、発生してしまった時の種類別の対処法などより深く掘り下げて解説していきます。
水草水槽マニュアル
【アンチグリーンを使った新しいコケ対策と除去】
アンチグリーンを添加し、葉の表面をクリーニングすることによって、再び水草が成長することがあります。本ページではそのメカニズムや、使い方や注意点、具体的な事例をご紹介します。